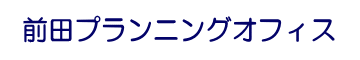信託のメリットは「環境の変化」に柔軟に対応できること
~人生100年時代、思いが変わるのは自然なこと~
◆ 環境も心境も、変わるのが当たり前
信託を活用する大きなメリットのひとつは、「将来の変化に柔軟に対応できる仕組み」であることです。
たとえば、こんな場面を想像してみてください。
– 最初は独り暮らしだった親が、子ども家族と同居を始めた
– 円満だった夫婦が、後に離婚して別々の道へ進んだ
– 自宅で暮らしていたが、介護付き施設に移ることになった
これらはすべて、「環境の変化」です。
そして、その環境の変化に伴って、「心境」も変わっていきます。
◆ 決めたことを、あとで変えたくなることもある
信託契約を組んだ当初は、「こうしたい」「これが最善だ」と思っていても、
実際に時間が経ち、状況が変わると、「今の暮らし方に合わなくなってきた」と感じることがあります。
そんなとき、信託は“修正”が可能な制度です。
この柔軟性が、他の法的な制度(遺言など)と違う、信託ならではの強みです。
◆ 具体的な事例:同居するようになった息子に資産を託したい
ある高齢の女性が、はじめは「二人の子どもに均等に財産を相続させたい」と信託を設定しました。
しかし、病気で身体が不自由になったのをきっかけに、長男が同居し、献身的に介護をしてくれるように。
その後、女性はこう思うようになります。
「この子に、もっと多くの財産を託したい。生活を支えてくれているんだから…」
このように、「気持ちが変わる」ことも、信託では前提にするべき変化です。
信託は、受益者代理人や受益者変更権者といった「調整役」を制度の中に組み込むことで、
こうした変化にも柔軟に対応できるように設計できます。
◆ 信託は「契約者の言う通り」にするだけの仕組みではない
信託は単なる「契約通りに運用される機械」ではありません。
本当に大切なのは、委託者が望んだ“目的”を、長期的に守っていくことです。
だからこそ、信託を設計する専門家の役割は重要です。
「将来、どんなことが起きるか」
「本人の意思が変わったとき、どう動けるようにしておくか」
その想定と準備こそが、信託設計の“プロの仕事”なのです。
◆ 認知症や意思能力の低下にも備えられる
もし、将来本人が認知症などで判断能力を失ってしまったら?
通常の契約では、変更も対応もできなくなります。
しかし、信託には、あらかじめ不測の事態を見越しておける設計力があります。
これこそ、家族信託が「人生100年時代のインフラ」と言われる理由です。
◆ まとめ:「本人の意思が変わる」ことを前提に信託を設計する
人の暮らしも、気持ちも、ずっと同じではいられません。
だからこそ、変わる前提で仕組みを作っておくことが大切なのです。
信託の本当の価値は、「その時の本人の思い」に寄り添い続けることができる点にあります。
信託の柔軟性を最大限に活かすことで、「安心」と「自由」が両立する人生設計が可能になります。